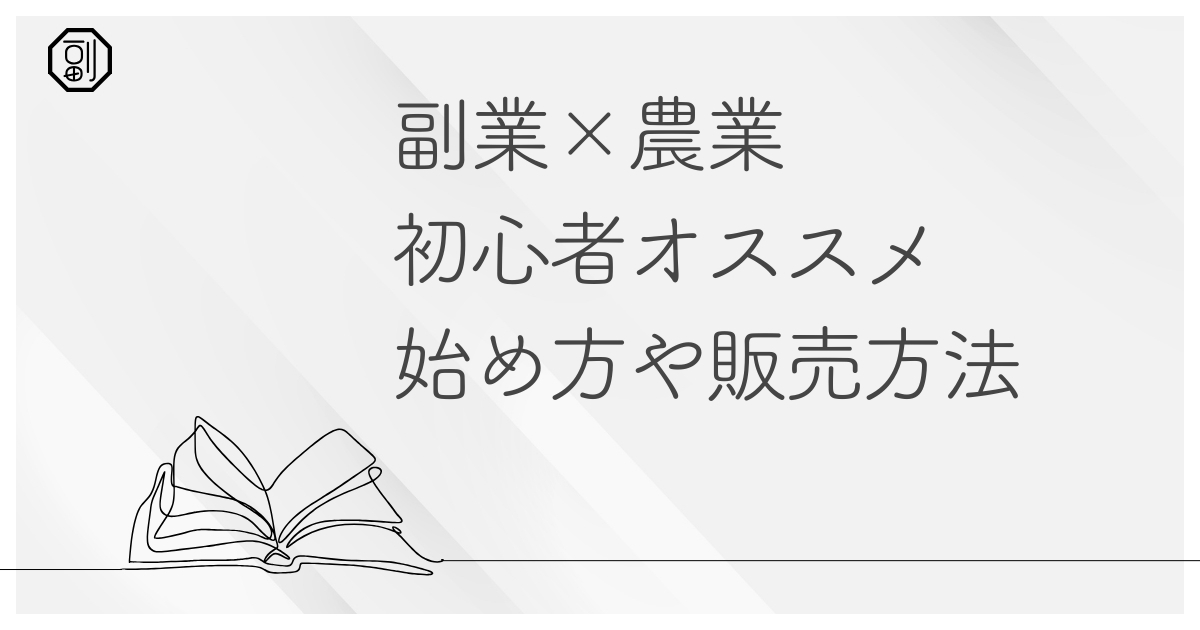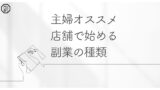近年、物価高騰が続く一方で賃上げが難しい状況にあり、生活の不安を感じる人が増えています。
食費がかさむ中、自分で野菜を育てることは家計の助けとなり、同時に健康や趣味にもつながるとして農業が改めて注目されています。
さらに、余った野菜を販売することで収入アップも可能です。
本記事では、副業と農業を両立する「兼業農家」という新しいライフスタイルについて詳しく解説します。
兼業農家とは何か、そのメリット、始め方、初心者でも育てやすい野菜、販売方法まで、実践的なポイントをわかりやすくまとめました。
都会に住んでいても、地方に暮らしていても、あなたに合った副業農業の形を見つけられるはずです。
兼業農家とは?
近年、副業解禁の流れやリモートワークの普及により、「副業として農業を始めたい」と考える人が増えています。
兼業農家とは、本業を持ちながら空いた時間に農業に取り組む人々のことです。
たとえば会社員を続けながら週末に畑を耕したり、家庭菜園で育てた野菜を販売したりする形です。
農業は単なる「食料生産」ではなく、自然とのふれあい、心身のリフレッシュ、そして家計の助けにもなるため、副業との相性が良い分野といえます。
また、趣味としても適しており、長く続けやすいことからおすすめです。
農業のメリット
副業と農業を組み合わせると、多くのメリットが得られます。
ここでは、都市部・地方の両方の視点、そして物価高騰時代ならではの価値について見ていきましょう。
都心でもできる副業農業
都市部に住んでいても、レンタル農園やシェア畑を活用すれば気軽に農業を始められます。
- 週末だけ通える
- 必要な農具が揃っている
- 初心者でも指導を受けられる
こうした環境が整っているため、土いじりに慣れていない都会の人でも安心です。
さらに、スペースが限られていてもベランダでプランター栽培をする方法があり、自宅で気軽に野菜作りを楽しむことができます。
プランター栽培なら、ミニトマトや葉物野菜、ハーブなどを無理なく育てられ、毎日の食卓に新鮮な収穫物を加えることが可能です。
都市生活の中に「小さな農業空間」を持つことで、家庭菜園の楽しさを味わいながら食費の節約や安心・安全な食材確保にもつながります。
また、都会での農業は同じ志を持つ人と出会うきっかけにもなり、コミュニティ作りの場としても魅力的です。
レンタル農園を通じて仲間ができれば、情報交換や収穫物のシェアなど、新しいつながりも生まれるでしょう。
地方だからこその良さ
一方、地方在住の人にとっては農業がより身近で、生活の一部として自然に取り入れやすい環境が整っています。
都市部と比べて土地が広いため、家庭用と販売用を兼ねた規模で栽培できるのは大きなメリットです。
庭先や空き地を畑にしたり、先祖代々の田んぼを活用したりと、地域資源を最大限に生かすことができます。
さらに、農業を通じて余った農産物を地域の直売所に出荷したり、近隣住民と物々交換したりすることで、地域コミュニティとのつながりが深まります。
農地を守り活用すること自体が、地域の景観や伝統を守ることにもつながり、結果として地域貢献にもなります。
また、自然豊かな環境で土に触れ、作物の成長を見守る時間は、ストレス軽減や心の充実をもたらしてくれます。
朝に収穫した野菜をその日の食卓に並べられる喜びや、四季折々の自然を感じながら作業する心地よさは、地方ならではの贅沢です。
加えて、地方は都市部よりも土地代や生活費が抑えられるため、コストをかけずに農業を続けやすいのも魅力のひとつです。
副業として始めた農業が、やがては本業に近い規模に発展する可能性も十分にあります。
物価高騰時代に強い「食の自給」
食材価格が上昇を続ける今、自分で野菜を育てられることは家計を守る大きな力になります。
スーパーで買うと高くつく野菜でも、家庭菜園や小さな畑で栽培すれば、ほぼ種や苗、肥料代だけで新鮮な食材を確保できます。
また、自分で育てた野菜は無農薬や減農薬にこだわることも可能で、市販のものより安全性や味わいで優れる場合もあります。
とれたてをその日の食卓に並べられるのは、農業ならではの贅沢です。
さらに、副業として農業に取り組むことで、余った分を道の駅や直売所、自動販売機で販売でき、ちょっとした収入源にもなります。
家族で食費を節約しながら、販売によってお小遣いを稼ぐ「一石二鳥」のスタイルです。
加えて、災害や輸入価格の高騰などで食料供給が不安定になっても、自分の手で食を確保できる安心感があります。
単なる節約や収入アップにとどまらず、食の安全と暮らしの安定を支える力として、「食の自給」が今あらためて注目されているのです。
農家になる方法
副業として農業を始める際には、大きく分けて「畑・田んぼで始める方法」と「プランター栽培で始める方法」があります。
畑・田んぼで始めるメリット・デメリット
メリット
- 大規模に栽培できる
- 多品種の野菜や米作りも可能
- 本格的に販売につなげやすい
デメリット
- 土地や設備への初期投資が必要
- 雑草や害虫対策に労力がかかる
- 天候に左右されやすい
プランター栽培のメリット・デメリット
メリット
- ベランダや庭先でも可能
- 初期費用が安い
- 家庭菜園感覚で始められる
デメリット
- 栽培できる量が限られる
- 販売用としては収量不足になりやすい
野菜の面白さ
野菜作りには、収穫の喜びだけでなく、「育つ過程を見る楽しみ」があります。
芽が出る瞬間、小さな葉が伸びる様子、そして色づいていく実など、自然のリズムに寄り添いながら日々の変化を見守ることで、普段の生活では味わえない感動が得られます。
さらに、品種によって味や香りが異なるため、同じトマトでも甘みが強いものや酸味が爽やかなものなど、まるで「性格の違う野菜」に出会えるのも醍醐味です。
自分の好みに合わせて栽培品種を選び、世界にひとつだけのオリジナル野菜を育てられるのは農業ならではの魅力でしょう。
一方で、野菜作りには難しさもあります。
天候の影響で思うように育たなかったり、害虫に悩まされたりすることも少なくありません。
しかし、その困難を工夫や経験で乗り越えて美味しい野菜が実ったときの達成感こそが、農業の大きなやりがいとなります。
失敗を繰り返しながらも少しずつ上達していく過程は、まるでゲームを攻略していくような面白さがあります。
つまり、野菜作りの魅力は「食べる喜び」だけでなく、挑戦と発見の連続にあるといえるでしょう。
野菜を売る方法
副業として農業を収益につなげるには、販売方法を工夫する必要があります。
道の駅で販売する場合
地域の特産品を扱う道の駅は、観光客や地元住民に直接販売できる場です。
新鮮さや手作り感をアピールしやすく、売れ行きも安定しやすいです。
具体的な方法・流れ
- 取り扱い先となる道の駅を調べる
- 自分の住んでいる地域にある道の駅を訪問して、「生産者募集」「産直コーナー出荷者募集」といった掲示がないか確認します。
- 道の駅の管理事務所か運営団体に相談して、どのような条件があるかヒアリングしましょう。
- 出荷・委託か買取かを決める
- 委託販売方式
- 野菜を道の駅に預け、売れたら売上の一部(手数料)を道の駅に支払います。
- 売れ残りは自分で持ち帰る必要があることが多いです。
- 買取販売方式
- 道の駅が直接あなたの野菜を買い取り、その価格で売ります。
- 売れ残りリスクは販売側(道の駅)が負うことが多いです。
- 委託販売方式
- 品質・出荷規格をそろえる
- 道の駅が求める規格(サイズ・見た目・包装など)があるので、それに合わせます。
- 食品衛生法・農薬残留基準などの遵守。生産履歴記録を求められる道の駅もあります。
- 価格設定と陳列方法を工夫する
- 道の駅では「新鮮さ」「地元産」「手作り感」が強みとなるので、それをアピールします。
- 売れ残った際の対応をあらかじめ確認しておきましょう(持ち帰り or 廃棄など)。
- 契約や出荷者登録
- 道の駅・直売所によっては「生産者・出荷者組合に加入」や「出荷会員登録」が必要なことがあります。
- 会費や出荷者登録料などがある場合もあります。
メリット
- 幅広い客層(地元住民だけでなく観光客など)にリーチできます。
- 自分で価格を提案できることが多く、利益率が比較的高めです。
- 自分の野菜のこだわりをアピールでき、「顔の見える農家」として信頼を築きやすいです。
デメリット・注意点
- 出荷規格が厳しいところがあり、ちょっとした見た目のキズなどで断られることもあります。
- 手数料・会費・出荷者登録費用などがかかる場合があります。
- 売れ残りリスクがあり、持ち帰りや処分の問題があります。
- 競合が多い可能性:同じ地域で似たような野菜が並ぶと差別化が必要です。
自動販売機での販売
最近注目されているのが「野菜の自動販売機」。無人販売が可能で、仕事の合間でも収入を得られるのが魅力です。
新鮮さを保つための工夫は必要ですが、効率的な販売スタイルです。
具体的なやり方
- 自動販売機を設置できる場所を見つけましょう(自分の農地近く、駅近く、住宅地近辺など)。
- 地主や施設管理者との交渉が必要です。
- 自動販売機のレンタル・購入、保守・補充、支払いシステム(現金・キャッシュレス)を用意します。
- 野菜の鮮度を保つ方法を確立します(保冷・湿度管理など)。
メリット
- 無人なので、人手を割かずに運営可能です。
- 時間の融通が利く副業向きです。
- 一度設置・仕組みができれば、定期的な補充で収益が見込めます。
デメリット・リスク
- 初期コストがかかります(販売機の設置・保守費用など)。
- 販売場所の認知度・通行数などが収益に直結します。
- 立地が悪ければ売上が伸びません。
- 盗難・いたずらのリスクがあるため防犯対策が必要です。
ネットショップで販売する場合
自社ECサイトや既存のECモール(楽天・Amazonなど)、または農産物特化型プラットフォーム(食べチョクなど)を活用すると、全国の顧客に直接販売できます。
SNSを組み合わせれば「顔が見える農家」としてファンを増やすことも可能です。
具体的な方法・流れ
- 販売先を決める
- 自社ECサイトを作るか、既存のECモールや農産物プラットフォームを利用するか選択します。
- 初心者はプラットフォーム利用が手軽でおすすめです。
- 商品ページを作成する
- 写真やキャッチコピーを工夫し、野菜の鮮度や栽培のこだわりをしっかり伝えます。
- 生産者のプロフィールや栽培ストーリーを載せると信頼感とリピート率が上がります。
- 発送方法を確保する
- 梱包方法、送料、鮮度保持(保冷剤やクール便など)を準備します。
- 配送スケジュールを決め、注文が入ったら迅速に発送できる体制を作ります。
- 宣伝・集客
- SNSやブログ、メルマガなどで販売情報を発信します。
- 料理レシピや栽培の様子をシェアするとファンが増えやすくなります。
メリット
- 全国の顧客にリーチできるため販路が大きく広がります。
- 自分の野菜のこだわりや栽培ストーリーを直接伝えられ、ファンをつくりやすいです。
- 自宅から販売ができるため、移動や人手が少なくても運営可能です。
デメリット・注意点
- 発送にかかるコストや手間が発生します。
- 写真や文章で魅力を伝える必要があり、宣伝やページ作成に時間がかかります。
- 注文量に応じた梱包・配送体制を整える必要があり、急な増加に対応できないと信頼を損なうことがあります。
JA(農協)を通して販売する方法
安定した販路と技術サポートがありますが、自由度が低く市場価格に左右されやすいです。
規模拡大を目指す人には向いています。
具体的な手順・仕組み
- JAへの加入
- 地元のJA組合員になる。会員制度があるので、まずは最寄りのJA事務所に相談しましょう。
- 共同出荷・共同販売
- JAは複数の農家から野菜を集荷し、品質・規格・サイズを選別し、卸売市場や小売店、スーパー、またはJAの直売所に提供する「共同販売」の仕組みがあります。
- JAが持つ販路やノウハウ、信頼性を活用できるメリットが大きいです。
- 契約内容・価格決定
- JAを通すと、価格の一部がJAの規定に基づくことが多く、あなたが自由に価格設定できない部分もあります。
- また、出荷規格を満たす品質が求められます。
- 出荷先の確認・ルートの選択
- スーパー・飲食店・市場などJAが持つルートを使います。
- また、最近はJA自身がネット販売(JAタウンなど)やJAの直売所を強化していて、こうしたチャネルを活かすことも可能です。
メリット
- 安定した買い取りが期待できます。
- 販路を自分で探す手間が減ります。
- JAが複数農家の野菜を集めて大量に出荷するため、流通コストや運搬コストの分散ができます。
- 品種選び・栽培法・出荷時期などで技術的なアドバイスやサポートといった情報提供があります。
デメリット・注意点
自由度が低い(価格や販売先、パッケージなどで自由に決められないことが多い)です。
価格が市場価格に影響を受けるため、収入が不安定になることがあります。
規格・品質の要求が厳しく、少しの傷やサイズが規格外だと「扱ってもらえない」こともあります。
自宅や小屋で販売する方法(直売スタイル)
副業農家にとって、一番手軽で始めやすいのが自宅販売です。
敷地の一角に無人販売所を作ったり、小屋をDIYして「地元直売所」のように見せれば、気軽に購入してもらえます。
店舗での副業についてはこちらの記事で詳しくまとめてあります。
自宅販売の仕組みづくり(看板・小屋DIY・無人販売所)
- 小屋をDIY:木材や古い物置を活用して販売スペースを作る
- 無人販売所方式:料金箱を設置し、購入者が自由に野菜を持ち帰れる仕組み
- 目立つ看板:道路から見える位置に「新鮮野菜販売中」と掲示すると集客効果が高まります
信頼感を高める工夫(価格表記・おつり・鮮度管理)
- 価格は明確に記載(例:1袋100円)
- おつり不要方式にして、トラブルを減らす
- 日差しや雨対策のために屋根・保冷ケースを用意
- 一言メモや「おすすめの食べ方」を添えるとリピーターが増えやすい
自宅販売のメリット・デメリット
メリット
- 初期費用が少なく始めやすい
- 販売の自由度が高く、自分で価格や陳列を決められる
- 地域の人とつながりやすい
デメリット
- 集客は基本的に「通りがかりの人」に依存
- 盗難や料金未払いリスクがある
- 季節や天候によって売上が左右されやすい
初心者でも簡単に育てやすい野菜
農業を副業として始めるなら、まずは初心者でも育てやすい野菜から挑戦するのがおすすめです。
育てやすい理由も含めて紹介します。
ミニトマト
プランターでも育てられるため、家庭菜園感覚で手軽に始められます。
日当たりの良い場所に置き、水やりと支柱の管理をするだけで十分収穫可能です。
比較的病害虫にも強く、肥料や剪定も少量でOKなので初心者でも失敗が少ないのが特徴です。
赤く熟した実はそのまま食べても、サラダや料理の彩りにも使えるため、家庭でも消費しやすいのもメリットです。
きゅうり
成長が早く、収穫量が多いので初心者でもモチベーションを維持しやすい野菜です。
ツルを支柱に誘引するだけで管理でき、肥料や水やりのコツもシンプルです。
夏場に特に育ちやすく、連作にも強い品種があるため、連続して収穫が楽しめます。
収穫したきゅうりは漬物やサラダ、炒め物など幅広く利用できるので、家庭でも余らせず使いやすいです。
葉物野菜(ほうれん草・小松菜など)
発芽から収穫までが短期間で済むため、初心者でも成長の過程をすぐに実感できます。
種まきが簡単で、プランターや畑の小スペースでも栽培可能です。
少量ずつ間引きながら収穫できるので、家庭で必要な分だけ収穫して新鮮なうちに食べられます。
生でサラダにしたり、炒め物やお浸しなどにも活用でき、食卓でも重宝する野菜です。
じゃがいも
病害虫に比較的強く、土さえあれば栽培可能です。
植え付け後は水やりと土寄せを少し行うだけで成長し、収穫も比較的簡単です。
収穫後の保存性が高いため、収穫時にまとめて取っても長期間保管でき、販売や家庭消費にも便利です。
さまざまな料理に使えるため、家庭菜園でも重宝されます。
ねぎ
手間がかからず、長期にわたって収穫できるため、初心者でも安定した収穫が可能です。
プランターでも畑でも栽培でき、土の管理さえしっかりしていれば成長も安定します。
追肥や間引きなどの管理も簡単で、1度植えると数か月から半年程度、必要に応じて少しずつ収穫できます。
薬味や炒め物など幅広い料理に使えるため、家庭でも便利な野菜です。
これらの野菜は、管理が簡単で収穫までの時間が短く、失敗してもリカバリーしやすいのが、初心者や副業農家に向いている大きな理由です。
Q&A:よくある質問
Q1:農業を副業にするには資格が必要ですか?
A:特別な資格は不要ですが、農地を借りる際には条件があるため、自治体や農協に確認しましょう。
Q2:どれくらいの初期費用が必要ですか?
A:プランターなら数千円から始められます。畑を借りる場合は数万円〜が目安です。
Q3:忙しい会社員でも続けられますか?
A:週末農業や自動潅水システムを使えば可能です。無理のない規模で始めましょう。
Q4:収穫した野菜はどうやって売ればいいですか?
A:道の駅、自動販売機、直売所、ネット販売など複数のルートを組み合わせると安定します。
Q5:農業で失敗しやすいポイントは?
A:欲張って大規模に始めること。最初は小規模で経験を積むのが成功の近道です。
Q6:副業農業で月いくら稼げますか?
A:規模や販売方法によりますが、月数千円〜数万円のプラス収入を得る人が多いです。
まとめ
副業と農業を組み合わせる「兼業農家」というスタイルは、これからの時代にますます注目される働き方です。
都会でも地方でも始められ、物価高騰への備えにもなり、心身の健康にもつながります。
まずは小さく始めて、自分なりのペースで続けることが成功の秘訣です。
ぜひあなたも「副業農業」という新しいライフスタイルに挑戦してみませんか?